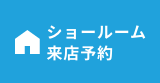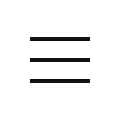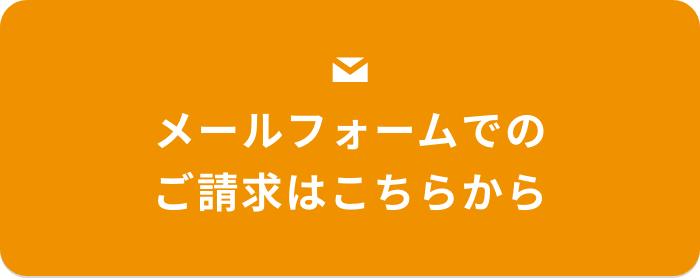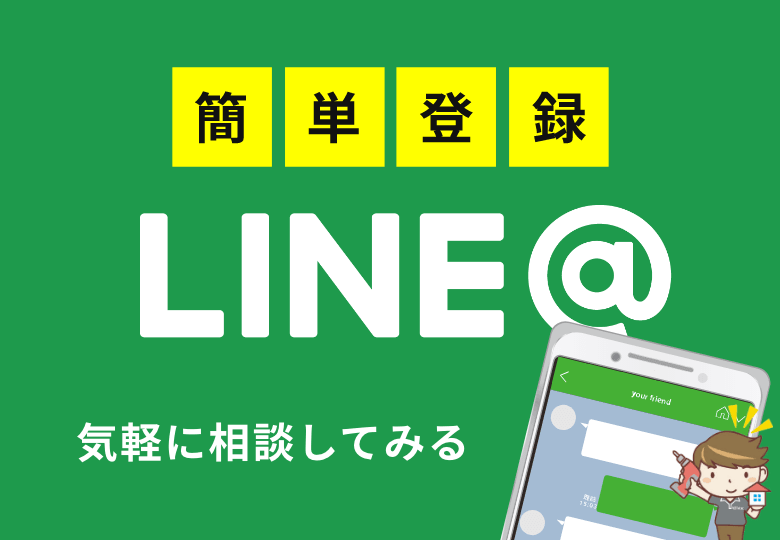2025/04/06
【床材をハンマーでブッ叩く!?】人気の無垢フローリング材5選を解説

【床材をハンマーでブッ叩く!?】
人気の無垢フローリング材5選を解説
(橋本)
リノベーションを人生最高の体験に!
こんにちは、ビスタの橋本です。
今回はみんな大好き無垢フローリングを題材にお喋りしていきたいと思います。
今回の企画のために商社さんにお願いしてサンプルもこの通り集めてきました。
いつも解説は1人だったんですが、今回は設計の菊池くんと大竹さんにも来てもらいました。
(菊池)
設計の菊池です。よろしくお願いします。
(大竹)
大竹です。お願いします。
(橋本)
無垢材って我々当たり前に商材として扱ってますけど意外とどこで採れてるかとかルーツって知らないよね?なんて思いまして。
どうですか?そのあたり。
(菊池)
(橋本)
今回は特に人気どころの5種をピックアップして掘り下げて行ければと思っております。
よろしくお願いします。
▪️オーク
(橋本)
まずはこちら、無垢フローリングでは定番中の定番「オーク材」です。
じゃあ早速解説いきましょう。
(まゆか)
オークとはブナ科コナラ属のうち落葉性の樹種を指し、
日本では「どんぐりの木」としてなじみ深いナラをはじめとしたカシワ・カシ・ミズナラなどの樹木の総称です。
(橋本)
オーク=ナラと思ってる方も多いんですけど、
ナラは中国・日本・ロシアが産地で、オークは北米産地になります。重さもちょっとオークの方が重いらしいです。
(まゆか)
他にも、ヨーロッパでは美しい樹形から、森の王様と呼ばれ、オークにまつわることわざや言い伝えが残っています。
ただし、日本の住宅建材として使われているオークは、
北米の亜熱帯から温帯で伐採された「ホワイトオーク」を加工したものが多くを占めています。
そのため、日本住宅に関する場合にはオーク材といえば、ホワイトオークを指すことがほとんどです。
オーク材は他の木材と比較すると耐水性が高く腐食や劣化の心配が少ないことから、
非常に古くより船材としても重宝されてきた歴史があります。
オークは耐水性だけでなく粘りや弾力があり加工しやすいという特徴を持っていて、
世界中でさまざまな用途に使用されてきました。
(橋本)
ウイスキーとかワインの樽にもよく使用されてますよね。
木は根っこで吸収した水分を導管で運んでいくんだけど、
オークはそこにチロースっていう風船状の物質が詰まっていて細胞内に水が行き渡るのに時間がかかるんですよ。
そういうわけで耐久性に優れていると。
(まゆか)
家具やフローリング材として使用する際には、オークの木目の美しさが大きな魅力となります。
オーク材を板目で取ると波状の美しい木目を楽しめます。
また、柾目で取った場合には優しい木目が穏やかな印象を演出します。
(橋本)
オークといえばナチュラルテイストのインテリアってイメージですよね。
最近流行りのジャパンディデザインにもオークがよく使われている印象です。
(まゆか)
オーク材を柾目に取ったときに見られる独特な木目として、「虎斑(とらふ)」が有名です。
まさに、虎の縞模様のような柄が表面に現れるのです。
虎斑は、オークが成長する際に蓄えた栄養分を貯めておく放射組織が
柾目の面に銀色の模様として浮かび上がったものと考えられています。
光の当たり具合によって見え方が変化する虎斑は、オークの表情豊かで個性的な木目として大切にされてきました。
銀色にキラキラと輝くことから、「シルバーグレイン」「銀杢(ぎんもく)」とも呼ばれる虎斑。
同じものは2つとないオリジナリティを楽しめるオークならではの特徴です。
(橋本)
虎斑は味があっていいですよね。無垢材好きにはたまらないと思う。
知らない人が見ると不良品かなと思っちゃうかもしれないですけどね笑
▪️チーク
(橋本)
次はチークです。
イメージとしては家具の方が定着してる気もするけど、床材としても人気が高いよね。
それでは解説お願いします。
(まゆか)
チークは、東南アジアの熱帯地域やインドに分布しているクマツヅラ科に属しています。
雨季と乾季がはっきりしているモンスーン気候の森で生育し、
樹高は40mほどにもなり、直径2mを超える大木に育ちます。
厳しい環境の中で育つこともあり、その耐候性には驚くべきものがあります。
ミャンマーには1752年に伐られたチークの原木が記念樹としてそのまま保存されており、
260年以上の時を経た現在もほとんど風化していません。
木材として加工されてもその特性は変わらず、優れた耐久性を発揮するチークは、
まさに世界を代表する銘木と言えます。
(橋本)
世界三大銘木と呼ばれる木がありまして、ウォルナット・マホガニー・そしてチーク。
高級木材のイメージがありますけど、天然木の伐採はすでに禁止されていて、
日本に来るのはエクアドル・インドネシアからの植林材になってます。
なので現在は手の届く価格になっているんだと思います。
(まゆか)
チークの大きな特徴は、耐水性が非常に高いことです。
チーク材は内部にタールを多く含み、油分が水をはじくため、高い耐水性を発揮しています。
その耐水性の高さから、古くは船の甲板や内装にも利用されてきました。
有名な事例では、豪華客船クイーンエリザベス2世号のブリッジや内装、大型練習帆船日本丸の甲板にも利用された記録があります。
(橋本)
オークもそうだったけど耐水性・腐朽性の高い木材は元々船によく使われてたんですね。
無人島に漂流したらオークかチークを探すといいかもね笑
(まゆか)
チーク材は、木目の美しさと経年変化で起きる色合いの変化もメリットの一つです。
耐久性・耐水性があるため、長い期間、繰り返し利用する床や天板、
内装材などに利用されていますが、年を重ねるごとに変化する色合いも楽しめます。
これはチークに含まれるタールが徐々に蒸発することで起きるといわれています。
生産されたばかりのチーク材は、比較的薄い色合いに、タールの成分による黒い模様が現れる木目です。
経年変化によってタールが蒸発すると、黒い模様が薄くなり、全体的に濃い飴色に変化します。
この色合いの重厚感を求めて、古材の需要が高いのも特徴といえます。
(橋本)
なるほど。チークの古材独特のあの黒さはタールだったんだね。
経年変化(パティナ)好きにはたまらないね。菊池くん好きでしょ?
(菊池)
(橋本)
古くみすぼらしくなっていくんじゃなく、時と共に味わいが出てくるっていうのも無垢材ならではの魅力ですよね。
▪️スギ
(橋本)
お次はスギです。
日本人にはお馴染みの木材ですね。
花粉のせいでちょっと嫌なイメージもありますが。
スギ花粉のピークは春なんだけど、なんか1年中スギのせいにされちゃってる印象ないですか?
木からぶわっと黄色い花粉が飛散する映像が目に焼き付いてるせいだと思うんだよね。
少し脱線してしまいましたが解説お願いします。
(まゆか)
まっすぐに伸びた幹と、大きいものは数十メートルにまで達する杉(スギ)は、日本だけに自生する固有の品種です。
日本各地に数多く群生している固有種「杉(スギ)」は、室町時代から植林されてきた歴史があり、
ほとんどが人口的に造成されたものです。
一方で、自然環境のなかで自生し、数百年といった歳月をかけて育ってきた天然のスギ(杉)も少なくありません。
本州から九州地方まで幅広く分布し寒さにも強く、
東北地方の一部や鹿児島県屋久島は天然スギ(杉)の産地としても有名であり、高値で取引されています。
(橋本)
杉の名産地で思いつくのといえばなんだろうね?
秋田・奈良・静岡とかかな。東京だと多摩地区にいっぱい生えてるイメージ。
材木屋さんとの雑談では奈良の吉野杉を絶賛してましたね。
プロが言うくらいなのでちょっと興味出てきますよね。
(まゆか)
杉(スギ)は地面から垂直にまっすぐ成長する特性があります。
そのため、木材として加工した際に直線的な木目が現れ、見た目も美しいことから建具に多く利用されてきました。
杉(スギ)花粉は花粉症の代表的な原因物質としても知られていますが、
木材としての杉(スギ)材は花粉の影響を受けることはありません。
(橋本)
花粉症のひどい体質の人にとってはスギというワードに過敏ですからね。
花粉出ないので安心して使ってください。
(まゆか)
杉の芳香には鎮静作用・消臭作用があり、リラックス効果があります。
寝室に杉を使えば、ぐっすりと深い眠りに入りやすくなります。
ちなみに先ほどの「吉野杉」は、国産の杉材のブランドの1つで、奈良県の吉野林業地帯で採れる杉のことを指します。
室町時代頃から始まったとされる「吉野林業」では、節の無い木を作るため、
節の元となる枝を切り落とす「枝打ち」を行い、美しく質の高い木を育ててきました。
その伝統は今も受け継がれ、他の産地では珍しい無節の大きな板を取ることができる太い幹の杉が、
吉野の山では現在も育てられています。
(橋本)
赤みのある無節材が希少とされてるんだけど、吉野杉は木の成長をわざと成長を遅らせることでこの希少な無節材を他よりも多く採ることができるそうです。
吉野杉を採用したら「うちの床材はね〜」なんてうんちくを小一時間語れそうですよね笑
スギ繋がりだとよくパネリングで使うウエスタンレッドシダーあるじゃないですか?
シダーって直訳するとスギなんだけど、あれはヒノキ科で別の樹種になります。
名前は見た目がスギっぽいからとのことです。米杉とも呼ばれてたそうな。
▪️ウォールナット
(橋本)
お次は三大銘木でも出てきましたウォールナットです。
解説お願いします。
(まゆか)
ウォールナットは機能性の高さ・美しさの両面から、チーク・マホガニーと並ぶ世界三大銘木の一つです。
中でもウォールナットはツヤや深い色合い、整った木目など、
美しく耐久性も高いため、高級家具やフローリングなどの建材、楽器、工芸品などの材料に使われています。
ウォールナットは世界的に人気で需要が高いにもかかわらず、成長が遅いため希少価値の高い木材です。
家具や建築などに利用できる大きさに成長するまで、百年単位の年月が必要と一般的にいわれています。
成長が遅いことに加え、全ての木材を使用できるとは限らないため、
ウォールナットは入手困難かつ希少価値が高い木材といえるでしょう。
また、年々価格も高騰しており、今後もウォールナットの希少性はますます高まることが予想されます。
(橋本)
今調べたんですけど直販メーカーの価格でもオークやナラの大体1.5倍の価格ですね。
サイト上だとアジアンウォールナットとアメリカンウォールナットに分かれていて、
アジア産の方が若干お安くなっています。
(まゆか)
ウォールナットの最大のメリットともいえるのが、高級感ある深い色合いです。
他の木材にはない紫がかった濃い茶色は、高級感があり大きな存在感を放ちます。
その人気は、塗装でウォールナットに近い色合いにしている家具もあるほどです。
また、辺材は白っぽいため、色の濃淡から、ウォールナット材ならではの美しいマーブル模様が生まれます。
塗装や着色でマーブル模様を完璧に再現するのは難しく、ウォールナットの価値をより高めています。
木目がまっすぐ整っており、美しいのもウォールナットのメリットです。
ウォールナットの木はまっすぐに成長するため、まっすぐ整った奇麗な木目を生み出すのがほとんどです。
また、部分的に生まれる波状や巻毛状の木目が、まっすぐな木目と混じり合うことで、美しい表情を作り出します。
(橋本)
そういえばこの部屋の床もナラ材だけどウォールナット色のオイルを塗ってます。
マーブル色は確かに再現難しいですね。
この模様と色の濃さこそウォールナットの魅力なんだと思います。
なんとなくだけど男性が好むイメージですよね。
(まゆか)
耐久性が高く、傷や凹みが付きにくいことも木材としての魅力といえます。
物を落としたり食器を置いたりしても傷や凹みがつく心配がないため、
小さい子どもやペットがいる家庭でも、問題なく使用できます。
衝撃を受けても割れにくい性質を活かして、ライフル銃の銃床にも使われています。
(橋本)
確かにライフルの持つところってこの色だわ。へー。
(まゆか)
温度や湿度の影響を受けにくいのもウォールナットの利点です。
一般的に木材は温度や湿度の影響を受けやすく、特に無垢材は温度が低くなると収縮したり、
湿度が高くなると膨張したりと変形しやすいものです。
しかしウォールナット材は温度や湿度の影響を受けにくいため、ほとんど変形しません。
またウォールナットは表面が滑らかで、触り心地が良いことから質感の魅力もあります。
また使い込むことで磨かれ、段々とより滑らかな質感になっていきます。
(橋本)
ここまで聞くと高いのも致し方ないかなって気がしてきますね。
使い込むことによって磨かれるっていうのもいいですね。
ウォールナットのような歳の取り方をしていきたいと思います笑
裸足で過ごす人にとっては毎日気持ちいいだろうね。
▪️西南サクラ(カバサクラ)
最後はこちら西南サクラ。
解説お願いします。
(まゆか)
西南サクラは、カバノキ科カバノキ属の落葉広葉樹。
主に中国の西南部を産地とするため、産地の名をとって西南桜と呼んでいます。
名前に「桜」とついてはいますがサクラ類ではなく、カバ(バーチ)のー種。
カバ類は桜に材質や外見が似ていることから、「○○桜」という名称で材が流通していることが多くなっています。
(橋本)
さっき話したレッドシダーでもそうだけど、ややこしいよね笑
全然西南カバでもいいと思うんだけど。
(まゆか)
材としては緻密で粘りがあり、素直で加工しやすく、ほどほどの硬さも備えています。
滑らかな木肌、控えめな木目、ピンクがかった上品な色味も特徴のひとつ。
材によっては「縮杢(ちぢみもく)・波杢(なみもく)」と呼ばれる独特の模様が出ることもあります。
これらは光の当たり具合によって表情が変わり、薄い板であっても立体感を感じさせ、
希少な材として市場でも珍重されています。
見た目の美しさと実用性を兼ね備えたとても有用な材ですが、その割には手の届きやすい価格帯というのも、
西南桜の大きな魅力となっています。
(橋本)
赤みというよりはほんのりピンクがかってるんだよね。
優しい雰囲気でナチュラルテイストに合うところから人気が出ているのかなと思いました。
飴のような杢の質感は確かにいいですよね。
縮杢といえば個人的にはメープルのイメージだったけど、西南サクラでも出るんだね。
価格もかなりお手頃なのでこれは人気になるのも頷けるなと。
(まゆか)
さらに硬すぎず柔らかすぎない、中程度の硬さも特徴です。
杉やパインのような針葉樹では、傷や凹みができやすいことがありますが、
西南桜は紅葉樹なのでそれほど気にする必要はありません。
かといって、硬いフローリングにありがちな、「素足で歩くとひんやりする」「疲れやすい」ということもありません。
無垢フローリングとして、とてもバランスが取れた材です。
また、西南サクラは年数を経ても、杉やパインほど飴色に変化することはありません。
ほんのりと色が深みを増す程度で、ごくゆるやかな変化となっています。
(橋本)
傷や凹みに弱い針葉樹最大の弱点を補って、紅葉樹のデメリットも感じづらいと。
経年変化もゆるやかなのは建材としては優秀ですよね。
変化を楽しみたい方には少し物足りないかもしれませんが。
・硬さを実験してみよう
はい、ここまでいかがだったでしょうか?
樹種は大きく分けると紅葉樹と針葉樹に分かれます。
紅葉樹は硬くて重く頑丈。
針葉樹は柔らかくて軽いけど、中に空気層が多いので断熱性が高い。
見た目とかなんとなくの重さは動画でも伝わるかと思うんですけど、耐久性ってちょっと伝わらないかなと思いまして今回・・・ハンマーでぶっ叩いてみようと思います。
詳しく見たい方はこちらをクリック(URL貼り付け)
(橋本)
今回は人気のフローリング材5選をご紹介いたしました。

ビスタでは「中古+リノベーションで日本の住まいと暮らしをリデザインする」というミッションを掲げています。
中古購入とリフォーム・リノベーションのお役立ち情報を発信していきますので、
ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
購入相談やリノベーションのプランニングに関しては概要欄にあるLINEからお申し込みください。
ご視聴いただきありがとうございました。
失礼いたします。